 |
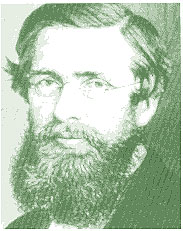 |
 |
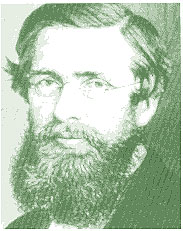 |
乮Wallace乯丂僂僅乕儗僗偵偮偄偰偼怴嵢徍晇巵偵傛傞堦楢偺廳岤側挊嶌丒東栿彂偑偁傝傑偡丅
丂傾儖僼儗僢僪丒俼乮儔僢僙儖乯丒僂僅儗僗乮1823乣1913擭乯偼丄僟乕僂傿儞乮偺傎偆偑14嵨擭挿乯偲摨帪戙丄撈帺偵帺慠慖戰愢傪峫偊弌偟偨僀僊儕僗偺攷暔妛幰偱丄亀儅儗乕彅搰亁亀摦暔偺抧棟揑暘晍亁亀擬懷偺帺慠亁側偳傪挊偟偰偄傑偡丅僟乕僂傿儞偲摨偠偔儔僀僄儖偺亀抧幙妛尨棟亁丄儅儖僒僗偺亀恖岥榑亁偐傜塭嬁傪偆偗丄帺慠慖戰愢傊偲摫偐傟偨偙偲偼丄楌巎偺嫟帪惈偺椺偲偟偰傕傛偔庢傝忋偘傜傟偰偄傑偡偑丄堢庬壠偵傛傞昳庬夵椙偲慖敳傪丄榑徹偵梡偄偨揰偱丄棟榑偵懳偡傞幏擮偼僟乕僂傿儞偺傎偆偑敳偒傫偱偰偄傞傛偆偱偡丅崱惣嬔巌偼丄偟偐偟丄堢庬壠傪帩偪弌偝側偐偭偨偲偙傠偵僂僅乕儗僗乮僂僅儗乕僗丄儚儔僗偲傕栿偡乯傪擣傔偰偄傑偡丅妋偐偵恖堊搼懣偲婡夿榑揑側帺慠慖戰偵偼乽恖娫偺堄巙乿偲偄偆揰偵偍偄偰棟榑揑偵妘愨偟偰偄傞偺偱偡丅僟乕僂傿儞偼乽帺慠慖戰乿偲偄偆偲偒偵丄惗暔摨巑偺嫞憟偲偄偆堄枴偵帇揰傪岦偗偰偄傑偡偑丄僂僅儗僗偼庡偵乮惗暔偲乯帺慠娐嫬偲偺偁偮傟偒傪峫偊偰偄偨偲偄偆嵎堎傕巜揈偝傟偰偄傑偡丅僟乕僂傿儞榑偑丄屄懱嵎傪傕偲偵曄堎傪榑偠偰偄傞偺偵懳偟偰丄僂僅儗僗偼摉弶丄崺拵側偳偺乽庬乿偺撪晹乮暘椶忋偺壓埵僇僥僑儕乕乯偵偡偱偵偁傞乽垷庬乿傪庢傝忋偘丄偦偺垷庬偲娐嫬偲偺乮崱偱偄偆乯搼懣埑偵傛偭偰庬偺暘婒偑婲偙傞偲偟偰偄傑偡丅偦偺偨傔丄摿偵僟乕僂傿儞偺惈慖戰乮僋僕儍僋偺旤偟偄塇崻偼丄帗偑旜塇崻偺棫攈側梇傪慖傃偮偯偗偨寢壥偱偁傞偲偄偆乯愢偵偼摨堄傪帵偝側偐偭偨傛偆偱偡乮偙偺棟桼偼丄慜弎偺恖堊慖戰偲帺慠慖戰偲偺揘妛揑憡堘偲椶帡偺堎幙惈傪攃埇偟偰偄偨偐傜偲巚偄傑偡乯丅
丂桞暔榑傪昗偠偰偄側偑傜摦暔偵傛傞惈慖戰傪帩偪弌偡偙偲偵偮偄偰丄偦偺桿榝偼傛偔傢偐傝傑偡偑丄揘妛揑偵偼晄壜巚媍側偙偲偱偡丅
丂僂僅儗僗偑僟乕僂傿儞埗偵憲偭偨帺慠慖戰偵偮偄偰偺榑暥乽曄庬偑傕偲偺僞僀僾偐傜尷傝側偔墦偞偐傞孹岦偵偮偄偰乿偑丄僟乕僂傿儞偵亀庬偺婲尨亁偺弌斉傪寛抐偝偣偨偲偄傢傟丄僟乕僂傿儞偑僂僅乕儗僗偺撪梕傪櫁愞偟偨偲偐丄僂僅儗僗傪僟乕僂傿儞偵徚偝傟偨抝偱偁傞偲偄傢傟傞偙偲傕懡偄偺偱偡偑丄僟乕僂傿儞偑帺愢傪挿擭乮20擭乯抔傔偰偄偨偙偲偼帠幚偱偁傝丄偙偺偙偲偵娭偟偰偼帺暘傛傝庒偄僂僅乕儗僗偺柤梍傪婥偯偐偭偰偄偨傛偆偱偡丅傑偨丄僂僅乕儗僗傕僟乕僂傿儞偵宧暈偟丄帺慠慖戰愢傪乽僟乕僂傿僯僘儉乿偲屇傇側偳丄偙偺忳傝崌偄偺懺搙偑丄愭庢尃偺憟偄偑懡偄壢妛巎偺側偐偱丄旤択偺堦偮偵悢偊傜傟偰偄傑偡乮扐偟怴嵢巵偼僂僅乕儗僗偑恑壔偺朄懃傪敪尒偟偮偮丄僟乕僂傿儞偵岟愌傪忳傞懺搙偵偮偄偰丄乽偟偐偟巹偲偟偰偼丄斵乮僂僅乕儗僗乯偺尓嫊偝偵偼搙傪挻偟偨偲偙傠偑偁傞偲偄傢偞傞傪偊側偄丅乿偲彂偄偰偄傑偡丅幚偼僂僅乕儗僗偑恑壔榑偺慶偲側傞壜擻惈傕偁偭偨傛偆偱偡仺亀恄旈偺朄亁乮岾暉偺壢妛弌斉乯乯丅
丂僟乕僂傿儞偲戝偒偔偨傕偲傪傢偐偮偙偲偲側傞揰偼丄僂僅儗僗偑摦暔偲恖娫乮惛恄)偲偺娫偵丄暍偄偒傟側偄娫寗傪尒偰偄偨偲偙傠偱偡丅僟乕僂傿儞偑恖娫丄摦暔傪娧偔朄懃偲偟偰帺慠慖戰傪寴帩偟偨偺偵懳偟丄僂僅儗僗偼恖椶偵帺慠慖戰愢傪摉偰偼傔傞偙偲傪尵偄弌偟偨傝偼偟傑偟偨偑屻擭偼嫅斲偟丄偙偺偙偲偑僟乕僂傿儞傪屗榝傢偣傞偙偲偵側傝傑偡丅僂僅儗僗偑桞暔榑揑側巚峫偵傛偭偰撥偭偨栚偐傜偆傠偙傪棊偲偡偒偭偐偗偵側偭偨偺偼丄嵜柊弍巘傗怱楈弍巘偲偺岎棳偱偁偭偨偺偱偡丅栚偵尒偊側偄楈懚嵼偑偍傛傏偡徴寕揑帠幚偑丄椙怱偁傞壢妛幰傪枹抦側傞傕偺傊偺扵媮偵偄偞側偄丄埲屻媫懍偵僗僺儕僠儏傾儕僘儉傊偺孹搢傪尒偣傞傛偆偵側傞偺偱偡丅
亅亅曗懌
丂僂僅儗僗偑丄挻帺慠尰徾偵怗傟偨偒偭偐偗偼丄偐側傝憗偄帪婜偲偄偄傑偡丅埲棃僀僊儕僗偺摉帪偺抦幆恖傪擬拞偝偣偨崀楈夛偵弌惾偟丄屻擭乽怱楈尋媶嫤夛乿偺愝棫偵彆椡偡傞側偳僗僺儕僠儏傾儕僘儉偺晛媦傕偟傑偟偨丅恖娫偺惛恄傗抦惈偵傑偱帺慠慖戰愢傪峫偊傞偙偲傪嫅斲偟丄嵟斢擭偵偼帺慠慖戰埲忋偵丄楈揑偱栚揑榑揑側憂憿椡偑恑壔傪摫偄偰偄傞偙偲傪婰偟偰偄傑偡丅1910擭偺亀惗柦偺悽奅亁偱偼丄嵃偵傛傞恑壔丄栚揑榑偑塎偊丄乽偁傜備傞偲偙傠偱栚偵尒偊側偄椡傗塣摦偑偼偨傜偄偰偄傞偙偲傪姶偠偲傞偙偲偑偱偒丄傑偨偦偙偐傜丄恑壔偺庡梫場偨傞悞崅偱嫮椡側亙巜摫嵃丟僨傿儗僋僥傿僽丒儅僀儞僪亜偺懚嵼傪椶悇偡傞乿偨傔偵恖娫偼偁傞偺偩偲偄偆偙偲傪弎傋偰偄傑偡丅乽恄旈巚憐偲楈揑恑壔榑乿峳枔岹亀恑壔榑傪桖偟傓杮亁暿嶜曮搰傛傝亅亅
丂僂僅儗僗偺挊嶌亀怱楈偲恑壔偲亁乮挭暥幮乯偼怱楈尰徾傪丄棟榑揑偵傕壢妛揑偵傕梚岇偝傟偆傞傕偺偲偺徹柧傪偮傜偹偨彂偱偁傝丄崱偲側偭偰偼偁傝傆傟偨僆僇儖僩曎岇榑偺傛偆偵傒偊傑偡偑丄偙偺楈揑娤揰偑丄帺慠慖戰枩擻庡媊偵帟巭傔傪偐偗丄恖娫惛恄偺懜尩傪媬偭偨偲偄偊傞偱偟傚偆丅僂僅儗僗偺峫偊偲偼媡偵丄尰戙偺恖娫偵帺慠搼懣乮奣偹恖堊搼懣偱偁傞乯傪擣傔傛偆偲偟偨摦偒偑丄偄傢備傞幮夛僟乕僂傿僯僘儉傊偲塭嬁傪梌偊丄20悽婭偵埫塤傪姫偒婲偙偡偙偲偲側傝傑偡丅
丂僂僅乕儗僗偵傛傞恑壔榑奣愢乮亀庬偺婲尨傪傕偲傔偰乮拀杸彂朳乯亁<怴嵢徍晇丟挊>偵丄2榑暥偺東栿偑廂榐偝傟偰偄傑偡両慺惏傜偟偄両乯
僒儔儚僋榑暥
丂僟乕僂傿儞偺亀庬偺婲尨亁乮1859擭乯偵愭棫偮偙偲4擭丄僂僅乕儗僗偑1855擭乽Annuals
and magazine of natural history乿帍偵宖嵹偝傟偨榑暥乽On
the law which has regulated the introduction
of new species乮怴庬偺摫擖傪挷愡偟偰偒偨朄懃偵偮偄偰乯乿偺撪梕偵偮偄偰徯夘偟傑偡丅僒儔儚僋乮儃儖僱僆摍惣晹偺抧柤乯偱幏昅偝傟偨偨傔丄偦偺撪梕偑乽僒儔儚僋朄懃乿偲傕屇偽傟傑偡丅儔僀僄儖偑亀抧幙妛尨棟亁偵傛偭偰丄崱尒傞戝棨傗奀梞偑丄偢偭偲偦偺巔偱偁偭偨傢偗偱偼側偔丄嶳傗屛丄奀嫭側偳丄抧幙揑曄摦偑丄夁嫀壗搙傕壗搙傕孞傝曉偟偰丄崱偁傞巔偵側偭偰偄傞偙偲偼柧傜偐側偙偲偱偟偨丅偱偼丄偦偙偵偡傫偱偒偨偱偁傠偆惗暔偼偦偺曄壔偵懳偟偰偳偆偱偁偭偨偺偱偟傚偆丅傛傝怺偄峫嶡偱偼丄乽傕偭偲傕嬤墢側庬偼抧棟揑偵嬤愙偟偰尒弌偝傟傞乿偺偼壗屘偩傠偆偐偲偄偆栤偄偐偗偵側傝傑偡乮僟乕僂傿儞傕丄傾儊儕僇僟僠儑僂偺椙偔帡偨2庬乮儗傾A儊儕僇僫偲儗傾丒僟乕僂傿僯傿乯偑嬤愙偟偰偄傞偙偲偵摨條偺媈栤傪書偄偰偄傑偡)丅偦偺僸儞僩偼丄抧棟揑側條乆側惗暔偺懡條惈偲丄抧幙揑偵棫徹偝傟傞尰惗庬偵嬤偄惗暔壔愇偲偵偁傞偺偱偼側偄偐偲榑傪棫偰傑偡丅
丂---乽抧忋偵偍偗傞尰惗偺惗柦偺抧棟揑側暘晍偑丄抧昞偦偺傕偺偍傛傃偦偺嫃廧幰偺椉曽偺丄偙傟傑偱偺偡傋偰偺曄壔偺寢壥偱偁傞偵偪偑偄側偄偲偄偆偙偲偑傢偐傞乿---
丂偙偺榑暥偼丄惗暔偺懡條惈傪丄庬偺暘婒偺楌巎偵傛傞傕偺偲偡傞夋婜揑側撪梕傪傕偭偰偄傑偡丅惗暔偺嬻娫揑攝抲偲帪娫揑宱楬傪寢傃偮偗偰峫偊傜傟偰偄偰丄抧棟揑妘棧偵傛傞庬暘壔偑婛偵偁傜傢偝傟偰偄傞偺偱偡丅寢榑偲偟偰乽偁傜備傞庬偼埲慜偵懚嵼偟偰偄偨椶墢偺嬤偄庬偲嬻娫揑偵傕帪娫揑偵傕廳側傝偁偭偰弌尰偟偨偲偄偆朄懃乿傪懪偪弌偟偰偄傑偡丅偦偺曄壔偺儊僇僯僘儉偙偦偙偺帪揰偱偼愢柧偟偰偄傑偣傫偑丄偁傞庬乮悢庬乯偼丄乮夁嫀偺乯偁傞庬偵桼棃偡傞偲偄偆恑壔榑傪偡偱偵梡堄偟偰偄傑偟偨丅傑偨丄杮榑暥偼丄惗柦偼恑曕偺奒抜傪搊偭偰偒偨偺偐壓偭偰偒偨偺偐偲偄偆摉帪偺榑媍偵懳偟丄惗暔偑彊乆偵曄壔偟偰偒偨帠幚傪抂揑偵弎傋偨傕偺偵側偭偰偍傝丄恑曕傕戅壔傕僒儔儚僋朄懃偑揔墳偝傟偨尰徾偺堦柺偱偁傞偲偟偰偄傑偡丅僟乕僂傿儞偼丄偙偺榑暥傪抦偭偨儔僀僄儖偐傜乽愭傪偙偝傟傞偧乿偲拤崘偝傟偰偄傑偡丅
僥儖僫僥榑暥
丂僥儖僫僥搰乮儅儗乕彅搰丄僴儖儅僿儔搰偺惣乯偱彂偐傟偨乽曄庬偑傕偲偺宆偐傜尷傝側偔墦偞偐傞孹岦偵偮偄偰乿(1858擭乯偙偦丄乽僒儔儚僋榑暥乿偱偼弎傋傜傟偰偄側偐偭偨曄壔傪愢柧偡傞棟榑丄帺慠慖戰乮偲偄偆尵梩偼巊梡偟偰偄側偄)愢偵摓払偟偨榑暥偱偁傝丄偙偺憪峞偑僟乕僂傿儞偵撏偗傜傟偰丄斵偲偦偺廃曈傪偁傢偰偝偣傞偙偲偵側傝傑偡丅
丂壠抺傗嵧攟嶌暔側偳偼恖娫偺曐岇壓偵偍偄偰傛偆傗偔惗柦傪曐偪傑偡丅椺偊偽丄晛抜怘傋偰偄傞栰嵷側偳傕丄栰惗庬偐傜嬯傒惉暘乮奞拵偐傜怘傋傜傟側偄偨傔偺杊屼暔幙乯偑彮側偄丄庬偑弉偟偰傕棊偪側偄丄幚偑擃傜偐偄側偳恖娫偵偲偭偰偼桳棙偱偡偑丄奣偹怉暔偵偲偭偰偼抳柦揑側惈幙偑慖敳偝傟偰偄傑偡丅偱偡偐傜丄嵧攟庬傪栰惗偵栠偡偲丄傕偲偺尨庬偵栠傞孹岦偵偁傝傑偡丅偙傟偼帺慠奅偵偁偭偰庬偼晄曄偱偁傞偙偲傪帵偡傛偆偵尒偊傑偡丅帺慠奅偱傕偲偒偳偒敪惗偡傞曄庬傕摨條偵丄偨偄偰偄偼惗懚偵晄棙側婏宍偱偁傝丄偦偺宯摑偼偄偢傟傕偲偵傕偳傞偲巚傢傟傑偡丅偟偐偟丄僂僅乕儗僗偼丄壠抺偑尨庬偵傕偳傞嶌梡偲摨偠尨棟偵傛偭偰丄偁傞庬偐傜攈惗偟偨曄庬偑尦偺庬偐傜彊乆偵棧傟偰偄偔丄偲悇嶡偡傞偺偱偡丅嵧攟庬偑尨庬偵栠傞孹岦偲丄恑壔偲傪摨偠嶌梡偱愢柧偡傞偺偱偡丅
丂惗懚嫞憟
丂僄僒傪傛傝桳棙偵妉摼偡傞偙偲偲丄揋偐傜傛傝偆傑偔摝偘傞偙偲偲偑丄屄懱偲庬慡懱乮庬幮夛偵捠偠傞乯偺惗懚偵嵟傕戝偒偔娭傢傞梫慺偱偡丅偁傞崺拵偼偆傫偞傝偡傞掱嵦廤偱偒傞偺偵丄偁傞庬偼怱寣傪拲偄偱傕傎偲傫偳嵦傟側偄偲偄偆屄懱悢偺嵎偼丄偙偺惗懚嫞憟偺寢壥偲棟夝偝傟傑偡乮偙偺揰丄崱惣嬔巌偺偡傒傢偗偺棟夝偲堎側傝丄僂僅儗僗乮偦偟偰僟乕僂傿儞乯偼乽悢偺榑棟乿傪桪楎偺婎弨偵偟偰偄傑偡乯丅
丂屄懱悢
丂怘暔楢嵔偺忋埵庬乮崅師擏怘摦暔乯偼丄壓埵庬傛傝屄懱悢偑偐側傜偢彮側偄偙偲偑柧傜偐偱偡丅奺屄懱悢偺懡壡偼丄偦偺惗暔偺懡嶻彮嶻偲偼傎偲傫偳娭學偑側偄乮偲弎傋偰偄傞乯丅寢嬊丄屄懱悢偑懡偄庬傕彮側偄庬傕丄庬乮屄懱)偑懡嶻彮嶻偱傕丄屄懱悢偑堐帩偝傟偰偄傞側傜偽丄1偮偑偄偐傜2旵埲奜偼傒側巰偵愨偊傞偙偲偵側傝傑偡丅屄懱悢偺懡偄庬偼丄僄僒乮嫙媼僄僱儖僊乕乯偑懡偄偐傜偱丄僗僘儊丄奀捁側偳偱擣傔傜傟傞帠幚偱偡乮偙偙偱屄懱悢偺懡偄庬偲偟偰崌廜崙偺儕儑僐僂僶僩偑偁偘傜傟偰偄傑偡偑丄栺40擭屻帺慠奅偱偼愨柵偟偰偄傞偺偱偡両両乯丅寢嬊丄屄懱悢偑懡偄偲偄偆偙偲偼丄僄僒傪傛傝懡偔妉摼偡傞偙偲偲丄揋偐傜偺夞旔偑傛傝偆傑偄偲偄偆偲偄偆偙偲偱偁偭偰丄偙傟偼庬偺拞偺屄懱偲屄懱偺娫乮屄懱嵎偵傛傞乯偵偍偙傞偙偲偐傜悇嶡偟偰丄偁傞抧堟偺庬偲庬偺娫乮嬤墢庬娫偺嫞憟乯偵傕婲偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞偺偱偡丅偙偙偼億僀儞僩偺堦偮側偺偱偡偑丄偙偺悇榑偺弴彉偐傜偡傞偲丄乽屄懱嵎偵傛傞惗懚嫞憟乿偲偄偆偺偼杮幙偱偼側偔丄偄傢偽偍慥棫偰偱偁偭偰丄僂僅儗僗偼丄恑壔偵捈愙娭學偡傞奒憌偼乽庬乿偵偁傞偲傒偰偄傑偡丅屄懱娫嵎傛傝傕嬤墢庬娫偺宍懺丄廗惈偺嵎傪廳帇偟偰偄傑偡丅乮偟偐偟丄怴嵢巵偼傗偼傝屄懱嵎傪廳梫帇偟偰偄傞偲庴偗庢傜傟偰偍傝丄乽僂僅儗僗偑偄偐偵僟乕僂傿儞愢偵擏敄偟偰偄偨偐乿傪帵偡偨傔偺孥洖栚偵尒偊偰偟傑偆偺偱偡偑丄寢嬊丄敾暿偮偒偵偔偄棟榑怺峩偺娒偝偑丄僟乕僂傿儞榑傊偺堷偗栚偲娭學偟偰偄傞偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅乯
丂屄懱嵎偵拲栚偡傞乮僟乕僂傿儞榑乯偲偄偆偺偼丄嶰崙巙乮撍攺巕傕側偄椺偊偱偡傒傑偣傫乯偱偄偊偽丄憘憖偺晲椡偲丄楥晍偺晲椡側偳屄恖揑銸椡傪斾妑偟偰揔晄揔傪榑偠傞傛偆側傕偺偱丄庬娫嵎傪榑偠傞偲偄偆偙偲偼丄憘憖孯偲楥晍孯偺丄晲憰搙丄孯惂丄嶌愴丄巑婥丄暫鈰丄彨悆偺帒幙丄戝媊柤暘側偳傪専摙偟偰偄傞偙偲偵偁偨傝傑偡丅楌巎偵偍偄偰娭怱偑偁傞偺偼丄傕偪傠傫屻幰偱偁傞傛偆偵丄惗暔偺楌巎乮恑壔)偵偍偄偰傕屄懱嵎偱偼側偔丄庬偺乽儖乕儖乿偙偦廳梫帇偝傟傞傋偒側偺偱偡丅峔憿庡媊惗暔妛偺庡挘傕摨條偲巚偄傑偡丅
丂娬榖媥戣丅--怘暔偺妉摼偲帺屓杊塹偵傕偭偲傕揔墳偟偨庬偑丄屄懱悢偵偍偄偰桪惃傪摼傞偩傠偆丅媡偵偙傟偵宐傑傟側偐偭偨庬偼愨柵偵摓傞丅庬偺屄懱悢偺懡壡偼丄偙偺椉幰偺娫偵埵抲偡傞丅惗暔偺屄懱悢偼丄偦偺嶻巈悢偵娭傢傜偢丄僄僒偲揤揋偺惗懚嫞憟偺傆傞偄偵傛偭偰惂尷偝傟丄偦偺庬偺宍懺偲愴棯偺弌棃晄弌棃偵埶懚偡傞丅偦偺弌棃晄弌棃偼丄偦偺抧堟偵杮棃惗懚壜擻側屄懱悢偺斾妑偵傛偭偰掕検偝傟傞丅--偙偺傛偆偵榑傪恑傔偨偁偲丄偙偆偟偨嬤墢庬摨巑偺娭學偺尒捠偟偐傜丄庬撪晹偺恊庬偲曄庬乮崱惣巵偼偙傟傪撍慠曄堎庬[屄懱嵎]偱偼側偔丄垷庬[庬偲怴庬偺嵎]偲庴偗庢偭偰偄傞偺偼惓偟偄棟夝偲巚偆乯偺娫傊偺栤戣傊偲墳梡偟偰偄傑偡丅
丂揔幰惗懚
丂偁傞庬偺拞偵丄僄僒偺妉摼傗揋偐傜偺夞旔偵傛傝桳棙乮偨偲偊偽傛傝挿嫍棧偐傜僄僒傪扵嶕偱偒偨傝丄懱怓偑揤揋偐傜尒偮偗偵偔偄側偳乯側曄庬偑弌尰偡傟偽丄傕偲偺恊偲摨幙偺僌儖乕僾傛傝偄偢傟偼屄懱悢傪憹傗偡傕偺傕弌傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅偲偔偵丄抧棟揑側曄摦傗挿婜偺姳偽偮丄昘壨婜側偳偑偍偙傝尨庬偵晄棙偵摥偔娐嫬偵側偭偨応崌丄曄庬傊偺抲姺偑壛懍偝傟傞偲悇應偟傑偡丅
丂乽偄傑傗曄庬偑庬偵偲偭偰偐傢偭偨丅乿僒儔儚僋榑暥偱偼愢柧偱偒偰偄側偐偭偨恑壔偺婡峔傪偙偺榑暥偱僂僅乕儗僗偼愢柧偡傞偙偲偑偱偒偨偺偱偡丅寢嬊丄僟乕僂傿儞偺帺慠慖戰偺梫揰偱偁傞丄嘆屄懱嵎丄嘇夁忚側屄懱悢丄嘊惗懚嫞憟丄嘋嵟揔幰惗懚偺婡峔偑丄傗傗愻楙偼偝傟偰偄側偄偲偼偄偊榑弌偝傟偰偄偨偲偄偊傞偱偟傚偆丅嘍偺堚揱偵偮偄偰偼摿偵怗傟偰偄側偄偺偱偡偑丄乽塱懕揑側曄庬乿偲偄偆昞尰偑堚揱傪曪娷偟偰偄傞偲峫偊傜傟傑偡丅屄懱嵎偺堚揱條幃傪榑弎偟側偐偭偨揰傪傒偰傕丄僂僅乕儗僗偼屄懱嵎傪偦偺傑傑恑壔偺尨棟偲偼偣偢偵丄庬嵎傊偲堦搙榑偺奒憌傪恑傔偰偄傞偙偲傪巟帩偟偰偄傞傛偆偵庴偗庢傟傑偡丅
丂堦曽丄儔儅儖僋偵傛傞惗暔偺堄巚傪偔傫偩恑壔愢偵懳偟偰丄婡夿揑側愢柧偵傛偭偰斀敐偟偰偄傞揰偼丄僟乕僂傿儞榑偲摨摍偺帇揰偱偡丅愭偺榑暥傪尒偰傕僂僅乕儗僗偺偙偺帪婜偺懺搙偼娤嶡帠幚偐傜棟榑傪婣擺偟偰備偔乮堦斒揑側)壢妛揑巚峫傪敪婗偟偰偍傝丄撍慠巚曎揑偵側傞儔儅儖僋偵嫍棧傪抲偄偰尒偰偄偨偺偱偟傚偆丅懠偵傕僥儖僫僥榑暥偵偼丄揔墳偵娭偟側偄宍幙偺曐懚乮拞棫恑壔偺朑夎乯丄妋棪榑側偳偵傕怗傟傜傟偰偄偰丄埲崀偺恑壔榑偺懌庢傝傪尨愇偺忬懺偱彂偒棷傔傜傟偰偄傞傛偆偱偡丅
丂偙偙偱僂僅乕儗僗偼朻摢偺栤偄偐偗偵栠偭偰丄壠抺傗嵧攟庬傪栰惗偵傕偳偡偲尦偺尨庬偵栠偭偰偄偔婡峔偲丄恑壔偺婡峔偑偍側偠帺慠慖戰偵傛傞傕偺偲偄偆埵抲偯偗傪嵞搙偍偙側偄傑偡丅壠抺傗嵧攟庬偑尨庬偵愭慶偑偊傝偟偰偟傑偆棟桼傪丄庬偺晄曄惈乮恑壔偺斲掕乯偵傛傞傕偺偲偡傞偺偱偼側偔丄恑壔偺朄懃偵偟偨偺偱偡丅
丂僟乕僂傿儞偵偲偭偰恑壔偼丄庡偵栰惗庬傪慖敳乮恖堊慖戰乯偟偰昳庬夵椙傪峴偆曽岦惈偱峫偊偰偄偨偺偵懳偟偰丄僂僅乕儗僗偺恑壔偼丄壠抺偑帺慠忬懺偱尨庬偵栠偭偰偄偔偲偄偆媡偺曽岦惈傪帩偭偰偟偰偍傝丄帺慠慖戰偺巊偄曽偵戝偒側嵎偑擣傔傜傟傞偺偱偡丅偺偪偵僋僕儍僋偺梇偺忺傝塇偵娭偟偰惈慖戰愢傪僟乕僂傿儞偑採彞偟偨嵺傕丄僂僅乕儗僗偼丄杮棃偺僋僕儍僋偺塇怓偼攈庤側怓偱偁偭偰丄帗偺抧枴側塇怓偼憙偱棏傪壏傔偰偄傞偲偒偵栚棫偨側偄偨傔偺帺慠搼懣偵傛偭偰恑壔偟偨丄偲偄偆傛偆偵僂僅乕儗僗偺帺慠慖戰偺撪梕偼丄僟乕僂傿儞偲堘偄偑偁傞偺偱偡丅
| 丂乽帺慠奅偵偼偁傞乮棯乯曄庬偑傕偲偵側傞宆偐傜墦偔傊丄墦偔傊偲宲懕揑偵慜恑偡傞偲偄偆孹岦乮乯偑偁傞偙偲丄偦偟偰帺慠偺忬懺偱偙偺寢壥傪惗傒弌偡偺偲摨偠尨棟偵傛偭偰丄側偤壠抺偺曄庬偑傕偲偺宆偵愭慶曉傝偡傞孹岦傪傕偮偺偐傕愢柧偝傟傞乿乮僥儖僫僥榑暥) | 丂乽<慖戰>偺廤愊嶌梡偼丄偦傟偑曽朄揑偐偮媫懍偵側偝傟偨傕偺偱傕乮帞堢嵧攟壓偺壠抺壔傪巜偡乯丄柍堄幆揑偐偮娚枬偩偑偄偭偦偆岠壥揑偵側偝傟偨傕偺偱傕乮帺慠慖戰傪梊憐偝偣傞乯偼傞偐偵傑偝偭偨<椡>偱偁傞偲丄巹偼妋怣偟偰偄傞丅乿乮庬偺婲尨乯 |
| 僂僅乕儗僗 | 僟乕僂傿儞乮壓慄偼昅幰乯 |
丂
丂偙偺乽慖戰乿偺揔梡偑帡偰偄側偑傜傕椉幰偱惓斀懳偱偁傞偙偲傕丄僂僅乕儗僗偺鐣弰傪彽偒丄乽慖戰乿偲偄偆尵梩傪嬱巊偡傞僟乕僂傿儞偵懳偟偰峊偊傔側懺搙傪偲傜偣偨偺偐傕偟傟傑偣傫丅偟偐偟巹偼丄僟乕僂傿儞偵傛傞恖堊慖戰偲帺慠慖戰偺揘妛揑崿摨偼晄忦棟偱偁偭偰丄僂僅儗僗偵慖戰乮搼懣乯棟榑揔梡偺堦娧惈傪擣傔傑偡丅
丂嵟屻偵丄僂僅儗僗偺暥偼乽曄庬偑悢偵偍偄偰偼桪惃傪堐帩偡傞偵偪偑偄側偔乿乽曄庬偑昿斏偵弌尰偡傞偲偄偆斀榑偺梋抧偺側偄帠幚乿側偳丄曄庬偼嵟弶偐傜暋悢偺屄懱傪慜採偵偟偰偄傞傛偆偵撉傔傑偡丅堦旵偺撍慠曄堎庬偐傜彊乆偵偦偺堚揱宍幙傪屄懱孮偵憹暆偝偣偨傛偆偵撉傔傞昞尰偼偁傝傑偣傫丅偡傞偲丄僥儖僫僥榑暥偵偍偄偰偼丄曄庬偑尦偺庬偐傜棧傟偰備偔儊僇僯僘儉偼愢柧偟偰偄傑偡偑丄偦偺曄庬偑偳偺傛偆偵偁傜傢傟偨偐偲偄偆揰偵娭偟偰偼丄僟乕僂傿僯僘儉偲摨條丄撍慠弌尰偡傞偲偄偆偙偲偱愢柧偝傟偰偄側偄偲巚傢傟傞偺偱偡丅
丂傗偼傝丄恑壔偺戞堦尨場偲偟偰丄惛恄揑側堦寕傪擖傟側偗傟偽恑壔榑偑姰惉偟側偐偭偨偺偱偼側偄偐丄寢嬊丄儔儅儖僋偺偄偆摦暔偺撪揑姶姱側偳傕幪偰嫀傞偙偲偼側偐偭偨偺偱偼側偄偐丄偲巚偆偺偱偡丅
丂---乽戞堦偵丄塅拡偵恖娫傪挻偊偨丄敪払掱搙傪堎偵偡傞抦揑懚嵼偑偄傞偙偲丄戞擇偵丄偦偺抦揑懚嵼偺拞偵偼恖娫偺屲姶偱偼擣抦偱偒側偄偵傕偐偐傢傜偢暔幙偵摥偒偐偗傞偙偲偑偱偒傞傕偺偑偄偰丄尰偵傢傟傢傟偺惛恄妶摦偵塭嬁傪媦傏偟偰偄傞偲偺擇偮偺寢榑偵摓払偟丄偦傟傪墳梡偟偨応崌偵帺慠搼懣愢偩偗偱偼愢柧偱偒偢偵巆偝傟偰偄傞攷暔妛忋偺尰徾偑偳偙傑偱愢柧偱偒傞偐傪丄榑棟揑偐偮壢妛揑偵悇偟恑傔偰偄傞偲偙傠側偺偱偁傞丅偦偺乭巆偝傟偨尰徾乭偲巹偑娤偰偄傞傕偺偼椺偺亀帺慠搼懣愢亁Contributions to the Theory of Natural Selection 偺戞廫復偱婔偮偐巜揈偟偰偁傞丅乿僂僅儗僗亀怱楈偲恑壔偲亁---
丂忋暥偱徯夘偟偨亀帺慠搼懣愢傊偺婑梌亁乮1870乯偱偼丄恖娫傊偺帺慠搼懣偺揔梡傪斲掕偟偨偵偲偳傑偭偨偺偱偡偑乮弌斉屻偙傟傪撉傫偩僟乕僂傿儞偼丄嵞搙僂僅乕儗僗偺挊偵崲榝偝偣傜傟丄嬯廰偵枮偪偨庤巻傪彂偒憲偭偰偄傑偡乯丄偝傜偵丄屻擭亀惗暔偺悽奅亁乮1910乯偱偼丄乽怉暔偺惗嶻敪払偺忬懺偵偼丄昁偢偙傟傪巜摫摑撀偡傞帄崅塨抭偺惛恄偑偁傞偙偲傪昞帵偟丄偦偟偰丄偦偺挜徹偼丄捁偺塇栄傗崺拵偺曄懺偵偍偄偰偟傔偝傟傞傛傝傕丄傓偟傠峏偵柧椖側傕偺偑偁傞丅乿偲丄惗暔堦斒偺恑壔偵傕丄僨傿儗僋僥傿僽丒儅僀儞僪<巜摫楈丄巜摫揑惛恄>偺摥偒傪擣傔偰偄傑偡丅僄僋僩僾儔僘儉側偳暔幙偵塭嬁傪梌偊傞楈揑懚嵼傪幚徹偟傛偆偲偟偰偄偨偔傜偄偺恖偱偁傟偽丄恑壔傪摫偔偦偆偟偨懚嵼傕丄慡偔擮摢偵側偐偭偨傢偗偼側偄偲巚偄傑偡丅
---乽堦庬偺乽憂憿椡乿偑幚嵼偟偰丄暔幙偵偙傟摍偺晄壜巚媍側壜擻惈傪晩梌偟丄傑偨乽巜摫揑堄巙乿偑幚嵼偟偰丄惗暔偺敪堢傪堦曕堦曕偵桿摫巜帵偟丄側偍丄妋屃偨傞乽媶嬌揑栚揑乿偑幚嵼偟偰丄慡惗暔奅傪偟偰丄夁嫀偺塱偒抧幙妛揑帪戙偵榡傝丄偦偺恑壔敪揥偺挿掱傪捠偠偰丄拝乆偲偟偰昑傞偙偲側偔丄偙傟偵婣岦偣偟傓傞傕偺偱偁傞丅乿僂僅儗僗亀惗暔偺悽奅亁---
---乽偐偔偟偰変乆偼丄乽惗暔偺慻怐傪慻傒棫偰傞楈乿偲傕尵偆傋偒堦戉偺楈孮傪擣傔摼傞偺偱偁傞丅乿僂僅儗僗亀惗暔偺悽奅亁---
丂僂僅儗僗偺愢傪尒傟偽丄曄庬偑尦庬傪柵傏偟偰丒丒丒偲偄偆傛偆偵丄偺偪偵幮夛僟乕僂傿僯僘儉偑搒崌傛偔岆夝偟偨傛偆側夁寖側帺慠慖戰偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅庬偺宍懺偲愴棯偵傛偭偰偼尦庬傛傝傕乮曄壔偟偨乯娐嫬偵揔墳偟屄懱悢傪憹傗偡傕偺偑偁傞偩傠偆偲偄偆庬偺敪揥傗抲姺傪峫偊偰偄傑偡丅崱惣恑壔榑傕丄尦庬偐傜垷庬偑暘婒偡傞嵺丄挷榓揑側嫟懚傪庡幉偲偟側偑傜傕丄尦庬偑柵傃傞傛偆側忬嫷偑偁傞偙偲偼摉慠棟夝偟偰偍傝傑偟偨丅僂僅儗僗偑恑壔偺扨埵傪丄崱惣偺偄偆庬幮夛偺傛偆側峔憿丒婡擻偲偲傜偊偰偄偨偲偡傞側傜偽丄椉幰偺峫偊偰偄偨撪梕偼嬤偄傕偺偱偁偭偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傑偡丅
乮崱惣嬔巌偺悽奅乯