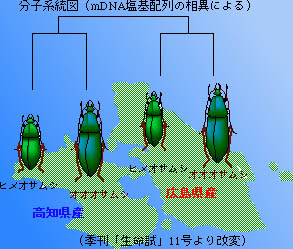アクセス解析
ロビタと有機体 ◆「ロビタ」とは手塚治虫さんの作品『火の鳥』に登場するロボットの名前です。手塚さんの作品には、どうしても人間としての優しさがにじみでていて、こうしたマンガを書き続けられたことに対してはなんとも言葉にならない感情で一杯なることがあります。『ジャングル大帝』やエッセイ『ガラスの地球を救え』を読み終わったときも、手塚治虫さん自身のメッセージに直接ふれるような思いがして、涙したこともあります。
ロビタは『火の鳥;未来編』に、この作品群を通して重要な役割をもつ猿田博士の助手ロボットとして登場しています。博士の内心を気遣う、忠実でとても人間的な性格をもっているのですが、それというのも、ロビタは単なるロボットではないからです。その出生の秘密は巻を変えて『復活編』に描かれています (これから『復活編』を読みたい人はこのページは避けてください) 。
「神よロビタを救いたまえ」 このシーン(原画切り抜き)は「孤独なロボット」ではなく、
『未来編』より
『復活編』では、ロボットと人間との関係をテーマとした年代の異なる二つの物語りがそれぞれ、年号のあるページを区切りに独立して描かれています。ところが最後になって、冒頭から登場しているチヒロを軸に、行き違う別々の物語りとして捉えていたものが、同じ話だったという真相が翻然とわかり、その手法に驚いた人は多かったのでないかと思います。しかも、物語りはそのまま『未来編』に登場していたあのロビタと同一のストーリーとして連結していたことを知るのです。ロビタの人間的な性格は、レオナ という青年の心に由来するものだったのです。
レオナ(左)と 融合されるロボット「チヒロ」 (右)はロビタを造ったウィークデー
物語りを詳細に述べずに話をすすめていくことは困難ですが、『火の鳥』を読んだことがある人は多いだろうと推測してこのロボットを題材にして有機体と進化論について考える材料を提供したいと思います。
ロビタは、人間の心を電子頭脳にもつ一台のロボットですが、時代が400年以上もくだりその秘密を知る人はいなくなりました。機械らしくない愛嬌のあるロボットということで、ロビタは記憶中枢も含めて複製され、どんどん数が増えてゆきました。同じ記憶を持つロビタは、同じ思い出と、同じ歌と、同じ遊びをおぼえていました。こうして便利なロビタが一日に520人ほど量産されるようになった時代のあるとき、ある富豪の家のロビタが子供を事故死させたという疑いをかけられ有罪となり、その家のロビタ全員が溶解処分されることが決定されました。
複製されるロビタ
このマンガのロビタの行動は、もと一つのものが分岐した子孫が、同時期に同様の変化をしてゆくという今西進化論が与える概念の一つに対して何らかのイメージを与えるものと思います。 今西錦司は、「個体はすなわち種であり、種はすなわち個体である」とも述べています。
ロビタが集団で自殺した原因は、一つのロビタを分解してしらべてもわからないでしょう。その原因はもと一つのものから分かれてつくられているというその歴史にこそあるのです。一部のロビタが理不尽な溶解処分をうけたからといって、別のところで働いているロビタが刑を受けたわけではありません。ですから、今まで普通に働いていたロビタが急に死を思い立ち、それが全世界に同時期におこるということは、不可解であり神秘的でもあります。私たちはこうした例を知っています。
生殖、このネオ・ダーウィニズムの進化論の要である遺伝子を子孫に伝えることによらず、形質や行動が受け継がれてゆくことがあるのでしょうか。一つの例は、ニューサイエンスと陰口をたたかれていますが、「百匹目の猿」に象徴される行動記録でしょう。イギリスのある街のシジュウカラが牛乳瓶のフタを開けてミルクを盗み飲みするようになってから、この習性がイギリス全土、そしてオランダやスウェーデンのシジュウカラにも伝播したという話もあります(反論は考えられるが・・・、ロビタの話に似てます)。この説明をニューサイエンティスト達は、形態形成場という仮説を立てて説明しています。
再出;当サイト7.今西進化論 より
一部のロビタの処刑によって、全世界に散らばった数万のロビタが同じ行動を起こしました。「元一つ」であるということから導ける今西著『生物の世界』にみられる思想は、こうした現象をなぞることができます。一見ばらばらに見える個が結びついて共動する原理はなんでしょうか。 「進化は種社会の分化による生物全体社会の生長である。」 (『自然学の提唱』)とは、今西錦司さんが進化に対して考えている概念をよくまとめてある言葉と思います。生物的自然という一大生物全体社会が、変転している雄大なイメージです。個と全体というテーマは、「個体差」のみを見ているだけでは、導き出されないものなのです。
2004.1
戻る